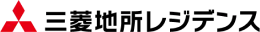一生ものの住まい建築家 大谷弘明さんが見た、
「ザ・パークハウス 京都鴨川御所東」の知恵。
2017年12月20日
古都の美意識を昇華した、新たな普遍の住まい。
連綿と受け継がれた日本の美意識が息づく京都。平安京の都として栄えた歴史が培った風雅の薫りが、今もそこかしこに漂う街。まさしく日本を象徴する地に、『ザ・パークハウス 京都鴨川御所東』は、あたかもずっとそこにあったかのような落ち着いた風情を醸し出している。
京都御苑・京都御所からも近く、鴨川の西岸に接し、東山連峰と向かい合う。京都の人々が愛してやまないこの地に、古都と同じ空気感を持つ〝邸宅〞をつくることが求められた。熟慮を重ねて、ついに、日本建築の粋を取り込んだ普遍的な美しさをたたえた住まいが完成したのだ。

厳しい景観条例をクリアした5階建ての低層建築は、直線を意識したデザインが印象的。軒庇に見立てたバルコニーの水平線、隔壁の垂直線、そして大きな寄棟屋根が美しいラインを描く。
2棟構成で、鴨川に面する別館「AKATSUKI―暁―」はすべて東向き住戸、三本木通りに面する本館「BIREI―美麗―」は北向きと南向き住戸に分かれている。
別館は、鴨川と東山の景観を楽しめるように、2階以上のバルコニーをガラス製の手すりにした開放的なつくり。一方、町家側の本館は、街並みに調和するようにシックな趣。ベージュトーンの織部焼タイルが、周囲の景観とも違和感なくなじむ。

エントランスホールには低い位置に窓を切り取って、内庭へと抜け感をつくっている。
エントランスは2か所で、どちらも日本建築の隅入りの作法にのっとっている。入口からまっすぐに建物内へ入るのではなく、あえて屈曲(クランク)を設けてアプローチを長く取り、奥へ奥へと誘う。これは、たとえば大徳寺の塔頭などに見られる手法。景観規制の関係で天井は低めだが、重心を低く取っているので圧迫感はなく、むしろ心が落ち着いてくる。シーンごとに変化をつけた格子や組子障子、京都の路地(ろおじ)を思わせる石の床などが目を楽しませる。外の植栽や内庭へと視線が抜けることで、空間が実際以上に広く感じられるのが巧み。
ガラスケースを取り払い、手の届くところに配された現代アートも、上質な空間に華を添えている。さらに、行き止まりにも見える屏風の背後にひっそりと佇む居心地のいいロビーと、内庭を望む離れのようなラウンジが用意されている。共用空間でもてなされた後は、プライバシーに配慮された“私邸”へと帰って行く。こうしたシークエンスに満ちたストーリー性ある演出も、建物の魅力を高めている。
外構や庭、共用スペースは華美に走らず、あくまで京都の品格を踏襲している“和”のエッセンスを取り入れつつもモダンに昇華されているので、現代人にとって居心地よく仕上がっている。日本の美を体現する“京都”への敬意をもって、細やかに練られた建築は、この得がたい立地で“一生ものに、住む”悦びを与えてくれることだろう。
四季折々の自然が美しい。鴨川の恩恵を受ける豊かな暮らし。

京都の街中を流れる鴨川を間近に感じる住まい。『ザ・パークハウス 京都鴨川御所東』では、誰もが憧れる風景を日常で愛でる贅沢が待っている。
岸辺の桜があたりをピンクに染める春、青い空と水辺の緑が鮮やかな夏、紅葉が彩り豊かな秋、ふわりと雪の舞うロマンチックな冬……。四季折々ばかりでなく、時間帯によっても様変わりする水辺の景色は、忙しい日々に疲れた心身を癒やし、風雅を愛する心を取り戻させてくれる。水音がもたらすリラックス効果は言うまでもないだろう。
鴨川西岸から見上げる、その昔、平安貴族たちも愛した東山の月。わざわざ河原に降りなくても、部屋にいながらにして月見ができるのは特権でもある。

鴨川沿いは桜の名所で、バルコニーの眼下にも並木が続く。
夏の風物詩、京都五山送り火のハイライト、如意ヶ嶽(大文字山)の大文字が真正面に鎮座。そもそも、当地周辺は平安時代に栄華を極めた藤原道長が法成寺を営んだ地だった。江戸時代の儒学者・頼山陽も居をかまえており、屋敷を「水西荘」、書斎兼茶室を「山紫水明処」と名づけて愛した。近くにある廬山寺は、『源氏物語』の作者・紫式部の邸宅跡。都の歴史を感じさせる京都御所の優雅な佇まいは、すぐ西に。

物件そばに鴨川の堰が。
風光明媚なだけでなく、河原町通と丸太町通に近いおかげで、中心街ならではの便の良さも享受。
一方では、大通りからは一本入っているので、静寂に包まれる。北に下鴨神社、東に平安神宮や岡崎公園、南に先斗町や祇園と、散策や食事の楽しみも尽きない。他でもない、鴨川のほとりに住むことで得られる豊かな日常が、ここにはある。

二条通から丸太町通に抜ける川沿いの遊歩道。

数百m南『ザ・リッツカールトン京都』傍を流れる鴨川の支流、みそそぎ川は蛍の生息地。

荒神橋から鴨川上流方面を眺める。

荒神橋の下、右河畔に『ザ・パークハウス 京都鴨川御所東』が見える。
ふたつとない環境と響きあう邸宅建築の妙。
日本建築に造詣が深く、京都の代表的な建物を手掛けてきた建築家、大谷弘明さんが2017年夏に完成した『ザ・パークハウス 京都鴨川御所東』を訪れた。
設計を担当した三菱地所設計の石井邦彦さんと三菱地所レジデンスの開発担当、菊田真悟の案内を受け、鴨川の最前列に建った新たなマンションについて語り合っていただいた。

大谷弘明(以下、大谷)
これは私の持論ですが、京都に建てるなら、スケールを小さくすべきだと思うんです。京都は街が細やかにできているので、建物も細やかさが求められる。東京の7割5分から8割が適切な気がします。
石井邦彦(以下、石井)
確かにそうですね。実は、日本建築の魅力、スケール感を以てマンションができないかとずっと思っていました。『ザ・パークハウス 京都鴨川御所東』は、それをつくるチャンスだったんです。
大谷
三菱地所レジデンスなら豪華にと望む人もいると思いますが、景観条例が厳しい京都では、真逆のチャレンジができるんです。天井が低いといった商品の観点では欠点とされることが、美点となります。面積が大きければいい建物ができるわけではないんです。
石井
むしろ、逆かもしれませんね。
大谷
この建物には、内庭を除くと吹き抜けがないでしょ?でも、息苦しさを感じないから成功しているんです。クランクが多いのも特徴ですね。
石井
クランクがもたらすシーンについては、特に意識しました。奥へ巡っていくごとに、空間が展開するようにしたかったんです。
大谷
特に、1階の廊下の構成はすばらしい。コンシェルジュデスクのそばで、廊下を少し遮るように壁から格子が出ていますね。そのため、反対側の内庭に視線が流れるわけです。そして、奥と手前の廊下とではデザインを変えている。組子障子の内側に間接照明を入れているのも巧みですね。
石井
このあたりの空間構成には、非常に時間をかけました。

コンシェルジュデスクの壁に、陶芸家・田嶋悦子氏の作品「FLOWERS」が彩りを添える。

1階廊下に配した格子から、右手の内庭に視線が流れる。

1階廊下の組子障子が麗しい。
大谷
それにしても得がたい敷地です。一期一会とはよく言うけれど、二度とない土地のために、建築家は全精力を傾けて設計するわけです。しかも、最初からあったように、あとあとまで愛される建物になるようにストーリーを持っていかなければなりません。私も鴨川前列に建つ『ザ・リッツ・カールトン京都』を手掛けるにあたり、京都の景観を左右する責任を感じました。
石井
そうですね。この敷地での設計は、やはり緊張します。場所に敬意を払い、きちんとした仕事をしたいという人たちが集まりました。自分で言うのも何ですが、出来たときから不思議と周囲にしっとりなじんでいます。
大谷
あたかも最初からそこにあったかのように見えることが、名建築の条件ですから。周囲の景観に入り込んで邪魔せず、自分が目立たないのは大事なこと。ここの築地塀も、あと数年したら周囲の環境を支えてくれますよ。

周囲の街並みに溶け込みつつ緩衝帯となる、多彩な植栽と築地塀。
――ここで開発担当、菊田真悟も加わり、図面を見ながら説明がされた。
菊田真悟(以下、菊田)
実は、京都では南に抜けているマンションが珍しいんです。南側のスパンが取れたので、本館の南向き住戸はゆったり住んでいただけるよう100㎡以上あります。
石井
本館の北向き住戸は50〜60㎡とプライベート感があり、鴨川側の別館は約120〜284㎡と特別感があります。
大谷
共用部の面積は、図面で拝見すると意外に小さいですね。歩いているときは、もっと広く感じましたが。
石井
重心を低くして、天井が低くても圧迫感が感じられないようにしました。空間の連続性や、植栽に抜けていく広がりも意識しています。
大谷
庭は大事な要素。建築の脇役と思いがちですが、「庭屋一如」の言葉通り、主従ではなくふたつでひとつなのです。『ザ・リッツ・カールトン京都』と同じ樋口造園の仕事なら、安心ですね。

ラウンジ「YUSUI―幽邃―」は"庭屋一如"を具現。

京都の樋口造園が腕を振るった内庭「SANSUI―山水―」。
石井
ここではアートシーンも重要です。京都のアートディレクターが選んだ7人の現代アートがガラスケースの垣根を越え、身近に置かれています。
大谷
マンションでは、ここまでアートを取り入れることはないのですか?
菊田
破損を懸念して額に入れたり囲いを設けたりするので、ここまで自然な形で置くことはあまりないですね。

アートが日常にある住まい。左は、辻村史朗氏の描いた屏風「土」と樂雅臣氏作の彫刻「輪廻 奏」。右は樂雅臣氏の「つくばい」。
大谷
大事なおもてなしですね。住人も招かれた客も、おもてなしゾーンを通るのは気分がいいでしょう。そして、鴨川に面した別館の住戸に入ると、8mを超える思いきった間口に切り取られた窓が広がっています。窓際に梁がないので、窓から見える風景がすべて自分のもの。通常、リビングに間仕切りを入れて部屋をつくりがちですが、そうしないのが功を奏しています。何より、バルコニーの手すりのラインが一本線で入るデザインがいいですね。
菊田
最近のマンションで、手すりを透明ガラスにするのは珍しいんですよ。
大谷
この場所は、透明でないと意味がないですからね。一方、本館は軒先を下げていくことで、各階が自分のところに屋根が付く感じです。この軒を下げていくのが京都風。野球帽を深くかぶるのが格好いいのと同じです(笑)。
菊田
なるほど(笑)。2つの棟の構造は、周囲の状況により異なっています。
大谷
私が好きなのは、別館最上階の左右の庇を切ってバルコニーの袖壁を取り、コーナーウィンドー風にしたところ。屋根が浮いて見えて豪華です。

鴨川に面した別館「AKATSUKI―暁―」の最上階は、袖壁を取ったバルコニーがコーナーウィンドー風に見える。
石井
京都市では原則、バルコニーに袖壁をつけないといけないのです。でも、ここは大事なところなので、最上階は外したいと京都市役所に交渉したところ、理解していただけました。
大谷
そうでしたか。ところで、これがあと2階分、高さを上げていいとなったら、ずんぐりとした建築になって美しくないでしょう。景観規制は、実は資産価値を上げてくれるのです。住める人も限られてきますしね。

本館5階のエレベーターホールから内庭を見下ろす。真正面に東山の大文字が。
菊田
鴨川に面した別館はわずか24世帯です。マンションの前には鴨川の堰があって、水の音もいいんですよ。桜並木が続いていて、春は2、3階から窓の外は一面のピンク。これはできてから気づいたのですが、本館の5階、エレベーターホールからも、東山の大文字が見えるんですよ。
大谷
そんな奥から大文字が見えるなんて、滅多にないことですよ。京都御所がなぜ東向きかというと、月が東から昇るため。往時の貴族たちにとって東は大事な方角で、東山の端に出る月を愛でた場所に住むのは最高の贅沢。この物件は高さを抑えられているけれど、極めてヒューマンスケールに合ったいい環境なんですよ。
石井
それと、夕刻のゆったりとした空気感は特に気持ちがいいので、そういう贅沢な時間も味わってほしいです。
大谷
石井さんとは初対面ですが、500m南の建物を担当したので無言のメッセージを交わしていた気がします。同じ方法論でもってつくったという思い。そして、このマンションの影響を受けた建物が出てきて、京都の街の景観がさらによくなればと思います。

町になじむ落ち着いた佇まい。

大谷弘明
株式会社日建設計 執行役員 設計部門副統括兼代表。日本文化への造詣を反映した『ザ・リッツ・カールトン京都』『宮内庁正倉院事務所』など多くの建築設計を手掛ける。『積層の家』で日本建築学会賞(作品)受賞。

石井邦彦
株式会社三菱地所設計 建築設計二部チーフアキテクト。『ザ・キタハマ』『グランフロント大阪オーナーズタワー』など数多く集合住宅を設計。『ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵』でグッドデザイン賞ベスト100受賞。

菊田真悟
三菱地所レジデンス株式会社 関西支店 事業企画部 計画第一グループ リーダー。広告宣伝の業務を経て開発部門へ。『ザ・パークハウス 京都鴨川御所東』では、着工時よりプロジェクトの全体統括として関わる。
ザ・パークハウス 京都鴨川御所東(分譲済)
● 所在地/京都府京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町197番11(地番)
● 構造・規模/鉄筋コンクリート造・地上5階地下1階
● 総戸数/85戸
●事業主/三菱地所レジデンス(株)
●設計・監理/(株)三菱地所設計
●設計協力(共用部内装・FFE)/(株)メック・デザイン・インターナショナル
● 管理会社/三菱地所コミュニティ(株)
● 施工/(株)熊谷組
● 竣工/2017年3月
photos by Satoshi Nagare
text by Miho Kitagawa
edit by Chikako Hara